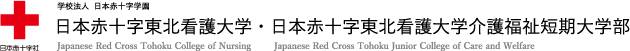2025年1月10日(金)午後1時より、「大学教育の質の保証・向上のための教職員研修会~大学設置基準改正を中心に~」と題したSD研修会を、FD・SD委員会の企画運営で開催しました。
「大学設置基準」は、大学としての研究および教育の施設、機能、運営が一定の水準を有するかどうかの基準等を定めた文部科学省令で、大学・学部・学科の設置という入口での質保証の基準(事前規制)であると同時に、法令で定められた自己点検・評価や認証評価(事後規制)での基準の中核を占める重要な法令です。2022年10月には中教審での議論に基づき、高等教育の質保証システム全体の見直しとして大規模な改正が行われましたが、本学ではこの省令について、どのような背景から改正が行われ、学内でどのような対応が必要になるのか、教職員に必要な知識及び技能を習得させ、能力や資質を向上させるための組織的な研修の機会が、決して十分とは言えませんでした。
そこで今回は、大学設置基準等改正に対する教職員向けSDを、これまで日本各地の大学に赴き実施して来られた、名古屋大学高等教育研究センター〔質保証を担う中核教職員能力開発拠点〕教務系 SD 研究会大学教務実践研究会に依頼し、東京都立大学理系管理課長(学務課長兼務)の宮林常崇さん、近畿大学 IR・教育支援センター准教授の竹中喜一さんを講師に迎えて、大学設置基準改正事項の解説講義に加え、それをどのように学内の関係業務に反映させるかを教員と職員が一緒に考えるグループワークを組みこんだ、対面型研修会の効果を最大限に高められる形式で研修会を企画しました。
この日の研修会は教員34名、職員18名、他大学教職員3名、計55名の参加があり、昨今の大学設置基準改正の背景と、改正による新たな概念である基幹教員制度の運用、単位数の設定方法等の解説があり、改正前後の変更点やモデルケースの事例紹介などにより具体的な対応方法が説明されました。また、今後大学で対応が求められる課題として、基幹教員制度運用の情報公開、主要授業科目の選定等の学内ルールの整備、「大学教育の質保証」であるディプロマポリシーと卒業要件の明確な関連付け等についても、大学の考え方を再整理することが必要であると付言がありました。グループワークでも活発な意見交換が行われるなど、大学設置基準改正における基幹教員の概念や実務対応への理解が深まるとともに今後の検討課題が共有され、今後の取り組みを理解する貴重な機会となりました。
参加者アンケートでは、全ての回答者から高い満足度が示されたほか、「学ぶものがあった」「視野が広がった」「自身の職務に役立つヒントが得られた」との感想が多く寄せられました。自由記述では〝主要授業科目について曖昧な理解をしていることに気づいた。また、基幹教員、主要授業科目、ディプロマ・ポリシーとの関連がよく理解できた〟〝学修者が何をどのように身につけることができたかを判断できる教育・質保証の在り方について理解を深めることができた〟〝以前の大学生像をそのまま現代の大学生に求めることが難しいと感じた〟〝指定規則による制約がある看護系学部に詳しい講師が来てくれた点が良かった〟〝次の改正時にも今回のような研修をタイムリーに受講したい〟など、具体的かつ率直な感想が数多く寄せられ、高等教育を取り巻く法令改正の趣旨を丁寧に理解し、正しく活用していく必要性を学内全体で理解できた貴重な機会となりました。