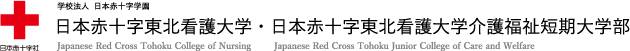東日本大震災。あれからもう14年。
この季節になると、あの日のことがいろいろ思い起こされます。
当時、私は、宮城県の大学に勤務していました。
あの日、14時46分、立っていられない大きな揺れが起きました。
バン!バン!とあちらこちらで閉まる防火扉の音が響き、
目の前の書棚から放物線を描いて、書籍が床に飛び散りました。
天井、壁のパネルがガチャガチャと崩れ落ち・・・停電が起きました。
教員ラウンジと講義棟をつなぐ渡り廊下に亀裂が入り、
講義室のテレビシステムが、机の上に落下して・・・。
その日は、後期入試の前日で、学生の立ち入りが制限されていたので、
大学の構内に学生はいなくてよかったと思いました。
でも、実家に帰っていた学生が、津波で命を落としました。
携帯電話のアンテナ基地局自体も損壊して通信サービスが途絶え、
学生の安否確認は、簡単ではありませんでした。
停電も続いていたので、携帯電話の充電ができないことも
安否確認を遅らせました。
安否確認の方法を検討し、定期的な練習の必要性が示唆されました。
あの震災では、多くの子どもたちが犠牲になりました。
朝、いつものように「行ってきます」と
元気に学校に行った子供たちが、
津波にのまれて帰ることはありませんでした。
三陸地方で伝えられてきた「津波起きたら命てんでんこ」を伝承し、
定期的に訓練していた地域のこどもたちは、それぞれに避難して
誰も生命を落とすことがなかったそうです。
発災から2週間目に、県の要請を受けて、津波被害地域の支援にでかけました。
海辺の街は、津波で壊滅し、大きな漁船が陸に乗り上げ、
地盤沈下のためか海面が高く、ところどころ亀裂の入った岸壁に、
津波の大きさと不気味さを感じました。
看護関連の支援は分担して、1件1件、家庭訪問で健康支援を行いました。
「家は無事だったけれど、職場が流されてしまって」
「うちだけ被害にあわずに、申し訳ない」など
生き残ったことへの罪悪感を語られた方もいました。
避難所では「生活不活発化」による「災害関連死」を防ぐ活動を行いました。
病院や施設の患者さんたちは、「上へ、上へ」と垂直避難が行われました。
震災遺構の「命のらせん階段」をみていると、
海水に浸りながら、避難する様子が目に浮かびます。
東日本大震災から14年。
災害サイクルに基づけば、30年後、1000年後に、
同様の地震がおきて、大津波が押し寄せます。
明日、大津波が発生するとわかっていたら、
みんな高台に逃げるのですが・・・。
災害は忘れた頃にやってくるので、
生命を守ることが難しかったりします。
「私たちは忘れない」「風化させてはいけない」等とよく言います。
何を忘れないのか、何を風化させてはいけないのか
今、東日本大震災で、何が起きたかを知り、
どのようなことが生命を守ることにつながるのか、
知識、技術、思考などを後世に伝え残すことができたらと思います。
日本赤十字秋田看護大学・日本赤十字秋田短期大学
学長 原 玲子
(日本赤十字秋田看護大学 赤十字教育委員会)