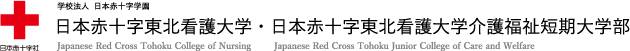主要科目の特長
合同研究ゼミナール
学生個々が現段階で考えている研究テーマあるいは、関心のあるテーマに関する内容、方法、意義等について学生が学籍を置く大学で個人指導を受け、その成果を集合して、5大学の学生・教員の前で発表することにより、学生が学籍を置く大学での個人指導がさらに深まり、博士論文作成に向けた糸口の発見や研究を遂行する過程での課題が抽出されるなど、今後の方向性が明確となります。また、交流の場をもつことで、博士論文作成に引き続き取り組む上での研究者としての資質を培います。
特別研究
関心ある専門領域の文献レビュー、研究の前提となる理論枠組みあるいは基盤を明確化し、テーマの選択、研究の目的、研究方法の選択、データの収集、結果の分析、考察など研究の一連のプロセス及び研究倫理に基づいた研究の取り組みについて指導します。
教育課程等の概要
| 科目区分 | 授業科目の名称 | 配当年次 | 開設大学 | 単位数 | 授業形態 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 必修 | 選択 | 講義 | 演習 | ||||
| 共通科目 | 看護理論 | 1・2前 | 日本赤十字東北看護大学 | 1 | ○ | ||
| 赤十字人道援助論 | 1・2後 | 日本赤十字東北看護大学 | 1 | ○ | |||
| 科学的研究方法論 I (実験研究) | 1・2前 | 日本赤十字北海道看護大学 日本赤十字九州国際看護大学 | 1 | ○ | |||
| 科学的研究方法論 II (臨床介入研究) | 1・2後 | 日本赤十字北海道看護大学 日本赤十字広島看護大学 | 1 | ○ | |||
| 科学的研究方法論Ⅲ (尺度開発) | 1・2前 | 日本赤十字北海道看護大学 日本赤十字東北看護大学 | 1 | ○ | |||
| 科学的研究方法論Ⅳ (質的研究) | 1・2後 | 日本赤十字北海道看護大学 日本赤十字東北看護大学 | 1 | ○ | |||
| 科学的研究方法論V (文化人類学的研究〉 | 1・2前 | 開講せず | 1 | ○ | |||
| 科学的研究方法論 VI (理論構築) | 1・2後 | 日本赤十字東北看護大学 | 1 | ○ | |||
| 臨床倫理論 | 1・2後 | 日本赤十字九州国際看護大学 日本赤十字北海道看護大学 | 1 | ○ | |||
| 小計(9科目) | 9 | ||||||
| 専門科目 | 看護人材開発特論 | 1・2前 | 日本赤十字豊田看護大 日本赤十字東北看護大学 日本赤十字九州国際看護大学 | 2 | ○ | ||
| 療養生活看護学特論 | 1・2前 | 日本赤十字東北看護大学 日本赤十字豊田看護大学 日本赤十字九州国際看護大学 | 2 | ○ | |||
| 生涯発達看護学特論 | 1・2前 | 日本赤十字豊田看護大学 日本赤十字北海道看護大学 日本赤十字東北看護大学 日本赤十字九州国際看護大学 | 2 | ○ | |||
| 実践看護学特論 | 1・2前 | 日本赤十字広島看護大学 日本赤十字豊田看護大学 日本赤十字九州国際看護大学 | 2 | ○ | |||
| 広域連携看護学特論 | 1・2前 | 開講せず | 2 | ○ | |||
| 災害救護特論 | 1・2前 | 日本赤十字広島看護大学 | 2 | ○ | |||
| 健康科学特論 | 1・2前 | 日本赤十字北海道看護大学 日本赤十字豊田看護大学 | 2 | ○ | |||
| 小計(7科目) | 14 | ||||||
| 演習 | 看護学演習 | 1通 | 日本赤十字北海道看護大学 日本赤十字東北看護大学 日本赤十字豊田看護大学 日本赤十字広島看護大学 日本赤十字九州国際看護大学 | 2 | ○ | ||
| 小計(1科目) | 2 | ||||||
| 合同研究ゼミナール | 合同研究ゼミナール | 1後 | 日本赤十字北海道看護大学 日本赤十字東北看護大学 日本赤十字豊田看護大学 日本赤十字広島看護大学 日本赤十字九州国際看護大学 | 1 | ○ | ||
| 小計(1科目) | 1 | ||||||
| 特別研究 | 特別研究 | 2~3通 | 日本赤十字北海道看護大学 日本赤十字東北看護大学 日本赤十字豊田看護大学 日本赤十字広島看護大学 日本赤十字九州国際看護大学 | 8 | ○ | ||
| 小計(1科目) | 8 | ||||||
| 合計(19科目) | 11 | 23 | |||||
授業科目の概要
| 科目区分 | 授業科目 | 概要 |
|---|---|---|
| 共通科目 | 看護理論 | 実践科学である看護学・看護科学の変遷を概観し、看護理論の役割・意義、および今後の課題を探究する。また、世界の動きに注目し、西洋と東洋を越えて統合された看護理論と実践に適用可能な中範囲理論を追究する。 |
| 赤十字人道援助論 | 授業の目的に沿って、主要国際機関の動向や赤十字機関が国内外で実施する人道援助の現状を歴史的な視点と具体的な活動事例も参考に学ぶ。 主な項目は以下のとおりである。 ➀国際人道支援の原則と赤十字の基本原則の役割・意義・貢献 ➁人間の安全保障とMDGsからSDGsの取り組み ➂武力紛争時に適用されるジュネーブ条約を中心とした国際人道法の体系 ➃国際的人道援の標準化と最低基準(スフィア・プロジェクト)、行動規範 ⑤緊急救援と開発協力の実際 | |
| 科学的研究方法論I(実験研究) | 実験研究に不可欠となる動物およびヒトの生体で起こる現象を科学的に立証するための研究方法、生体反応など様々なバイオマーカーを利用した実験研究及び準実験研究の方法について教授する。 | |
| 科学的研究方法論Ⅱ(臨床介入研究) | 臨床現場で介入による治療・ケアの効果を得るために臨床介入研究を計画し、遂行するプロセスについて教授する。介入のための方法論や結果分析法などについて実践的に教授する。 | |
| 科学的研究方法論Ⅲ(尺度開発) | 講義内容をもとに尺度開発に関する文献検討により深めた内容のプレゼンテーションとディスカッションを中心に行う。 | |
| 科学的研究方法論IV(質的研究) | 看護学における事象を帰納的な観点から探究するために必要な統合力を培い、学際的な研究手法を活用することの意味を理解し、現象学的研究及びグラウンデッド・セオリー・アプローチのプロセスを展開できるよう教授する。 | |
| 科学的研究方法論Ⅵ(理論構築) | 看護実践モデルを構築するためのプロセスと慢性疾患看護の実践場面における活用方法について、具体例を用いながら教授する。 | |
| 臨床倫理論 | 臨床現場で遭遇する倫理的諸課題に対して、社会的ニーズの多様化に即した適切な対処ができるよう、臨床倫理および医療マネジメントの基本原則と重要概念を教授する。看護学の領域において、今後の医療における倫理的役割の重要性と必要性を理解し、医療倫理と医療マネジメントを応用実践できるように敦授する。 | |
| 専門科目 | 看護人材開発特論 | 看護専門職実践の特徴を踏まえた人材開発を行うための看護教育や管理の諸理論について学ぶ。さらに看護の質を高め、継続教育を開発し、組織を統括できる人材育成を基軸に、看護教育プログラムやシステム開発を行うための方法論を探究し、課題を発見し、新しい知を構築する能力を修得する。 |
| 療養生活看護学特論 | 健康課題をもつ人々に対して、質の高い生活を支援するための療養生活看護に求められる専門的な技術、援助および教育方法などを探究する。 この探究を通して、専門領域における看護学の構築に向けて教授する。 | |
| 生涯発達看護学特論 | 生涯発達理論を基盤とし、人間の誕生から更年期までの対象において、それぞれの時期に必要な健康課題を明確にし、各段階に応じた生涯発達支援に向けた専門的な看護援助方法について、国内外の研究の知見を交えて教授する。また、小児期にある子どもの健康障害が成長発達に及ぼす影響と慢性疾患をもつ子どもと家族の支援に関する生涯発達理論・概念を教授する。 | |
| 実践看護学特論 | 脳卒中やがんなどの生活習慣病とともに療養生活を営む人間や健康に対する諸理論や既存の研究成果を概観し、成長発達段階と健康障害のレベルを融合した観点から、その人がより健康に生活していくための健康上の問題や研究課題を探求し発見する能力を修得する。 | |
| 災害救護特論 | 1)災害看護領域における現象や看護実践の分析、活用されている諸理論や先行研究の研究成果を概観し、災害サイクルの各期の質の高い看護ケアを行うための看護の理論や方法論について探究する。さらに、関心のある研究トピックに関する研究の動向や課題を探究し、研究方法論を検討する。 2)災害時における要配慮者の健康問題とそれに対するケアおよび介入方法について探究し、看護の役割を検討する。 3)災害急性期および復興期のケアに関する諸概念や方法論に関する文献を概観・分析し、質の高い看護を検討する。また、災害時における課題解決に向けた他機関連携、他職種連携について探究し、研究方法論を検討する。 | |
| 健康科学特論 | 地域や職域などの集団に介入して、そのウェルビーイングを高めることはヒューマンケアの目標のひとつである。このために、保健医療専門家は、集団を構成する多様な人たちの健康に関連する諸要因を、科学的・統計的に分析して、適切な介入方法を考案し、その実践をクリティカルに評価することが必要である。ここでは、国内外の知見を紹介し、全員で討議して理解を深める。 | |
| 看護学演習 | 看護学とその隣接領域において、国内外の文献を検討材料とし文献レビューを行い、より専門性を深めるとともに、各自の関心領域において課題解決が必要とされるテーマ、研究課題の明確化及び研究方法を検討する。さらに、課題解決に必要とされる理論と方法論、技法について実証的に探求す る手法を習得する。 | |
| 演習 | 合同研究ゼミナール | 学生個々が現段階で考えている研究テーマあるいは、関心のあるテーマに関する内容、方法、意義等について学生が学籍を置く大学で個人指導を受け、その成果を集合して、5大学の学生・教員の前で発表することにより、学生が学籍を置く大学での個人指導がさらに深まり、博士論文作成に向けた糸口の発見や研究を遂行する過程での課題が抽出されるなど、今後の方向性が明確となる。また、交流の場をもつことで、博士論文作成に引き続き取り組む上での研究者としての資質を培う。 |
| 特別研究 | 特別研究 | 関心ある専門領域の文献レビュー、研究の前提となる理論枠組みあるいは基盤を明確化し、テーマの選択、研究の目的、研究方法の選択、データの収集、結果の分析、考察など研究の一連のプロセス及び研究倫理に基づいた研究の取り組みについて指導する。 |
研究指導員
日本赤十字北海道看護大学
| 教授 安酸 史子 | 看護学生教育(特に実習教育)、患者教育(特に慢性期の患者教育)、看護師教育、看護教師教育についてケアリング理論を基盤に実践研究の方法論について探求する。 |
| 教授 西片 久美子 | 慢性疾患や認知症とともに生きる高齢者とその家族の支援に関する研究指導を行う。 |
| 教授 石﨑 智子 | 療養生活を送る人々およびその支援者のメンタルケアや精神障がい者支援の課題を改善・改革し、療養生活を営む人々がより良い生活を送ることができるような支援に関する研究指導を行う。 |
| 教授 志賀 加奈子 | 予防接種を受ける親子への支援および支援を提供する看護者へのサポートに関する研究指導を行う。 |
日本赤十字東北看護大学
| 教授 原 玲子 | 質の高い看護サービスを提供するための看護組織のあり方や看護職のキャリア開発、継続教育に関する研究指導を行う。 |
| 教授 新田 純子 | 慢性疾患とともに生活する人々への看護援助に関する研究指導を行う。 |
| 教授 志賀 くに子 | 思春期を中心とした健康教育のあり方や方法に関する研究指導を行う。 |
| 教授 高田 由美 | 在宅療養者や認知症高齢者の食生活を支える看護援助に関する研究指導を行う。 |
| 教授 阿部 範子 | 親の育児困難感を低減するために、親サイド・子どもサイド、また子育てを支援する家族や育児環境の視点から、解決策探求に関わる研究を支援する。 |
日本赤十字豊田看護大学
| 教授 鎌倉 やよい | 周術期にある人、摂食嚥下障害を有する人に対する看護ケアプログラムの開発を中心課題とし、主にシングルケースデザインに基づく介入研究を指導する。 |
| 教授 百瀬 由美子 | フレイル予防、認知症高齢者ケア、家族介護者支援、老年・在宅看護学領域における倫理的課題等に関する研究指導を行う。 |
| 教授 山田 聡子 | 看護基礎教育における看護倫理教育の在り方と方法に関する課題や、臨地実習指導における指導者役割と指導方法に関する課題に焦点をあてた研究指導を行う。 |
| 教授 東野 督子 | 医療関連や療養環境における感染を予防するための専門的な援助方法や、口腔ケア、教育プログラム、急性期状況にある人に関する研究指導を行う。 |
| 教授 野口 眞弓 | 在院日数の短縮化の中での母乳育児に関するケアの充実、および、それを支えるサポート体制づくりに関する研究指導を行う。 |
| 教授 大西 文子 | てんかんやネフローゼ等の健康障害をもつ小児とその家族の日常生活支援のための看護援助に関する研究指導を行う。 |
| 教授 カルデナス 暁東 | 自己免疫疾患など慢性疾患をもつ患者とその家族の療養生活における自己管理、また外見上に課題を抱える患者の生活の質を高める看護支援に関する研究指導を行う。 |
日本赤十字広島看護大学
| 教授 田村 由美 | IPWを基盤にした災害への備えに関する研究、災害時の避難所看護実践モデル開発に関する研究指導を行う。 |
| 教授 百田 武司 | 脳卒中や認知症などの高齢者やその家族の健康問題の解決やQOLを高める看護援助方法の開発・検証に関する研究指導を行う。 |
日本赤十字九州国際看護大学
| 教授 小松 浩子 | がんや慢性疾患とともに生きる人やその家族の支援、ならびに百寿者を含む高齢者の支援に関する研究指導を行う。 |
| 教授 姫野 稔子 | 老年期にある対象者や家族への支援および倫理的問題、看護介入の効果の測定ならびに看護介入プログラムや教育プログラムの開発に関する研究指導を行う。 |
| 教授 櫻本 秀明 | 小児から高齢者までを含むクリティカルケアをうける患者や、その家族の支援に関する研究指導を行う。 |
| 教授 髙橋 清美 | 精神障がい者の支援に関する研究、地域における精神疾患に関する課題に焦点をあてた研究指導を行う。 |
| 教授 永松 美雪 | リプロダクティブ・ヘルス/ライツの課題に関連する要因の分析、その支援と予防モデルの開発および評価に焦点を当てた研究指導を行う。 |
| 教授 本田 多美枝 | キャリア各期の特性に応じた人材開発の方法、リフレクションを活用した看護職の実践力開発の方法論、熟達化に関する看護モデル開発に焦点を当てた研究指導を行う。 |
履修モデル
履修モデル例1
| 区分 | 授業科目 | 履修方法及び修了要件 | 履修時期及び単位数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年次 | 2年次 | 3年次 | ||||||
| 前 | 後 | 前 | 後 | 前 | 後 | |||
| 共通科目 | 看護理論 | 2単位以上 | 1 | |||||
| 科学的研究方法論Ⅲ(尺度開発) | 1 | |||||||
| 専門科目 | 看護人材開発特論 | 選択必修2単位 | 2 | |||||
| 演習 | 看護学演習 | 必修2単位 | 2 | |||||
| 合同研究ゼミ ナール | 合同研究ゼミナール | 必修1単位 | 1 | |||||
| 特別研究 | 特別研究 | 必修8単位 | 8 | |||||
| 計15単位 | ||||||||
履修モデル例2
| 区分 | 授業科目 | 履修方法及び修了要件 | 履修時期及び単位数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年次 | 2年次 | 3年次 | ||||||
| 前 | 後 | 前 | 後 | 前 | 後 | |||
| 共通科目 | 赤十字人道援助論 | 2単位以上 | 1 | |||||
| 科学的研究方法論Ⅰ(実験研究) | 1 | |||||||
| 科学的研究方法論Ⅵ(理論構築) | 1 | |||||||
| 専門科目 | 災害救護特論 | 選択必修2単位 | 2 | |||||
| 演習 | 看護学演習 | 必修2単位 | 2 | |||||
| 合同研究ゼミ ナール | 合同研究ゼミナール | 必修1単位 | 1 | |||||
| 特別研究 | 特別研究 | 必修8単位 | 8 | |||||
| 計16単位 | ||||||||
履修モデル例3(長期履修課程)
| 区分 | 授業科目 | 履修方法及び修了要件 | 履修時期及び単位数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年次 | 2年次 | 3年次 | ||||||||
| 3年目 | 4年目 | |||||||||
| 前 | 後 | 前 | 後 | 前 | 後 | 前 | 後 | |||
| 共通科目 | 臨床倫理論 | 2単位以上 | 1 | |||||||
| 科学的研究方法論Ⅳ (質的研究) | 1 | |||||||||
| 専門科目 | 実践看護学特論 | 選択必修2単位 | 2 | |||||||
| 演習 | 看護学演習 | 必修2単位 | 2 | |||||||
| 合同研究ゼミ ナール | 合同研究ゼミナール | 必修1単位 | 1 | |||||||
| 特別研究 | 特別研究 | 必修8単位 | 8 | |||||||
| 計15単位 | ||||||||||