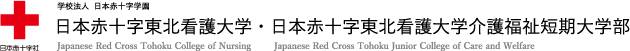アドミッションポリシー
入学者受け入れ方針:求める学生像
共同看護学専攻では、赤十字の理念である「人道(humanity)」のもとに、学際的な視野から独創的な学術研究により看護学の発展に寄与できる能力を備えた人材の育成を目指します。次のような資質と能力、意欲をもった人材を幅広く求めています。
- 赤十字の「人道(humanity)」の理念に共感し、高い倫理性を備え、多職種と協働しながら、看護を発展させる意欲のある人
- 修士の学位又は専門職学位を有する者と同等以上の学力を有し、保健・医療・福祉の専門知識を持つ人
- 独創的な研究に取り組むための基礎的な力を有している人
- 研究を遂行するための基礎的な英語の読解力を有する人
カリキュラムポリシー
教育課程の編成・実施に関する方針
共同看護学専攻の設置の趣旨及び教育目標を達成するため、科目区分を設け必要な授業科目を配置するとともに、当該科目区分ごとに履修要件単位数を定め、体系的なコースワークによる教育課程を編成しています。
- 看護学を導く理論を探求するとともに、高度な実践知を基盤とした理論を構築するための方法および研究方法を学修し、博士学位論文の作成に結びつけるために共通科目をおく。
- 看護における知識や技術の検証、新たな理論や方法論の創設等、より高度な研究能力を身につけ、広範な健康問題や看護課題について実践的な研究を行うために専門科目をおく。
- 自らの研究テーマに関わる事例や先行研究を分析し、課題解決のための理論と方法論、技法について実証的に研究する手法を探究するために演習をおく。
- 博士学位論文作成に向け、専門領域の垣根を越え異なる専門性の観点から、実現可能な研究に向けての方向性を明確化するために合同研究ゼミナールをおく。
- 保健・医療・福祉の場で科学的視点を持ち教育・研究能力が発揮できる高度専門職業人に必要な研究能力の修得を目指すため特別研究をおく。
ディプロマポリシー
学位授与に関する方針
修了要件となる単位を修得するとともに、博士論文の審査及び最終試験に合格し、次の条件を満たすものに博士(看護学)の学位を授与します。
- 看護学の専門性を探求し、学際的な視野から独創的な学術研究を自立して推進する能力を有している。
- 研究成果を発信し、社会に還元する能力を有している。
- 看護教育・研究・実践において、指導的立場を担い、看護学の発展に寄与できる能力を有している。
アセスメントポリシー
学修成果の評価の方針
共同看護学専攻博士課程における教育の成果を可視化し、学生の学修成果を適切に測定・評価するため、入学者受け入れ方針(アドミッションポリシー:AP)、教育課程編成・実施の方針(カリキュラムポリシー:CP)及び学位授与の方針(ディプロマポリシー:DP)の3ポリシーに基づいた評価指標を策定し、機関(大学院)レベル、教育課程(専攻)レベル及び科目(授業)レベルの3段階における、「入学時・入学直後」、「在学中」及び「修了時・修了後」の3時期で学修成果を評価する。
検証結果は、本課程の入学試験・カリキュラム、授業内容・研究指導とその方法及び学生の学修・研究活動支援の改善・充実等に活用する。
各ポリシーの評価指標
| 各レベル | 入学前・入学直後 APを満たす人材の検証 | 在学中 CPに即した学修の検証 | 修了時・修了後 DPの修得に対する検証 |
|---|---|---|---|
| 機関レベル | ・入学試験 | ・休学者数(率) ・退学者数(率) ・留年者数(率) ・各科目の成績(修得単位数) ・TA雇用率 ・RA雇用率 | ・学位授与数 ・就職率 ・修了生追跡調査 |
| 教育課程レベル | ・入学試験 | ・各科目の成績 (修得単位数) ・研究計画提出者数 (研究計画初稿提出から合格までの期間) ・博士論文提出者数 (博士論文初稿提出から合格までの期間) ・休学者数(率) ・退学者数(率) ・研究倫理研修の受講率 ・学会発表数 ・論文採択数 | ・修了認定者数 ・修了者の在学年数 ・学会発表数 ・論文採択数 |
| 科目レベル | – | ・各科目の成績 ・授業評価アンケート ・フィードバック | – |
注1:機関レベルの評価は、各大学で行う。
注2:教育課程レベル及び科目レベルの評価は、共同看護学専攻自己点検・評価委員会で行う。
アドミッション・ポリシー
各大学が,当該大学・学部等の教育理念,ディプロマ・ポリシー,カリキュラム・ポリシーに基づく教育内容等を踏まえ,入学者を受け入れるための基本的な方針であり,受け入れる学生に求める学習成果(学力の3要素※)を示すもの。 ※(1)知識・技能,(2)思考力・判断力,表現力等の能力,(3)主体性を持って多様な人々と協働して学ぶ態度 ポリシーの策定に当たっての個別留意事項 ディプロマ・ポリシー及びカリキュラム・ポリシーを踏まえるとともに,「学力の3要素」を念頭に置き,入学前にどのような多様な能力をどのようにして身に付けてきた学生を求めているか,入学後にどのような能力をどのようにして身に付けられる学生を求めているかなど,多様な学生を評価できるような入学者選抜の在り方について,できる限り具体的に示すこと。また,必要に応じ,入学前に学習しておくことが期待される内容についても示すこと。
ディプロマ・ポリシー
各大学がその教育理念を踏まえ,どのような力を身に付ければ学位を授与するのかを定める基本的な方針であり,学生の学修成果の目標ともなるもの。 ポリシーの策定に当たっての個別留意事項 ・ 各大学の教育に関する内部質保証のためのPDCAサイクルの起点として機能するよ う,学生が身に付けるべき資質・能力の目標を明確化すること。 ・ 「何ができるようになるか」に力点を置き,どのような学修成果を上げれば卒業を認定し,学位を授与するのかという方針をできる限り具体的に示すこと。その際,学士課程答申で示された「各専攻分野を通じて培う学士力~学士課程共通の学習成果に関する参考指針~」を踏まえるとともに,日本学術会議の「大学教育の分野別質保証のための教育課程編成上の参照基準」等も参考とすることが考えられること。 ・ 学生の進路先等社会における顕在・潜在ニーズも十分に踏まえた上で策定すること。
カリキュラム・ポリシー
ディプロマ・ポリシーの達成のために,どのような教育課程を編成し,どのような教育内容・方法を実施するのかを定める基本的な方針。 ポリシーの策定に当たっての個別留意事項 ・ ディプロマ・ポリシーを踏まえた教育課程編成,当該教育課程における学修方法・学修過程,学修成果の評価の在り方等を具体的に示すこと。その際,能動的学修の充実等, 大学教育の質的転換に向けた取組の充実を重視すること。 ・ 卒業認定・学位授与に求められる体系的な教育課程の構築に向けて,初年次教育,教養教育,専門教育,キャリア教育等の様々な観点から検討を行うこと。特に,初年次教育については,多様な入学者が自ら学修計画を立て,主体的な学びを実践できるようにする観点から充実を図ること。
アセスメント・ポリシー
学生の学修成果の評価(アセスメント)について、その目的、達成すべき質的水準及び具体的実施方法などについて定めた学内の方針。